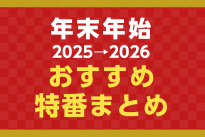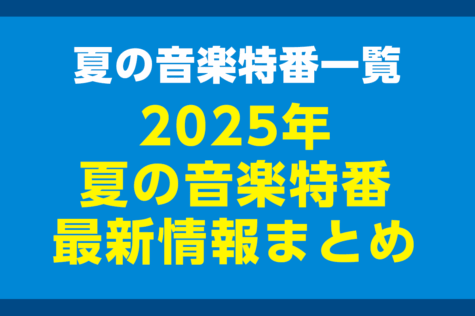7月19日(土)午後2時から8時間にわたって生放送されるTBS系夏の大型特番『音楽の日2025』。今年の番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたい。そんな熱い思いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”でみんなの心を震わせてくれる名曲を歌唱する。
そんな『音楽の日2025』において、アーティストが輝くステージを作り上げている中川清志さん(技術プロデューサー兼照明デザイナー)と宇野宏美さん(美術プロデューサー兼美術デザイナー)。今年の『音楽の日』ならではの見どころや、美術・技術スタッフだからこそ味わえる喜びなどを語ってくれました。
◆『音楽の日』の美術・技術を支える“匠”であるお2人。普段はどのようなお仕事をされているんですか?
中川:僕は音楽番組を中心に、照明の光の強さや位置、色を決めています。演者さんの後ろにライトをおいてキラキラに見せるとか。そういう作業をやりつつ、技術プロデューサーという立ち位置から、カメラマンや音声さん、編集マンたちの配置もしています。
宇野:私は大きく言うとセットを作る仕事なんです。ただ、実際に作るのは大道具さんたちの仕事で、私はその前段階として演出サイドと打ち合わせをし、イメージスケッチや図面を書いて。セットの大きさや素材も決めて、それを基にセットを作ってもらうんです。並行して美術チーム全体のスケジューリングをしながら技術陣と話し合い、完成まで持っていく感じです。
◆『音楽の日』の場合、どのような流れで作られているんですか?
中川:『音楽の日』はもともと、東日本大震災からの復興のために立ち上げた番組なんです。15回目になる今回もその思いは含みつつ、テーマの「ココロ」をどう具現化するか話し合いをして。
宇野:音楽番組は結構、そういう作り方をすることが多いんです。バラエティだと先にセットを作ったものに技術スタッフがアプローチすることもあるんですけど、音楽番組は美術と技術の両チームが一つになり、みんなでゼロから育てていくという。
◆「ココロ」というワードだけで全てを作り上げるのは難しそうですし、まずは演出サイドの聞き取り調査をしながらイメージを固めていく感じでしょうか。
宇野:そうですね。どれだけ引き出しを開けられるか勝負みたいな(笑)。それで少し抽象的ですが、視聴者の心を動かし、何かを感じてもらえる空間を目指そうと。アーティストと融合して、彼らを映えさせることも意識しながらセットを考えています。
中川:おそらく8時間の番組の中で「心ときめく時間」「心震える時間」といろんな心を見せていくんだろうと解釈して。ただ、セットはほとんど変えようがないので、僕ら照明やカメラマンが世界観を切り取って、違うように味付けしていくというか。総合演出の竹永典弘さんは「きっかけ」という言葉を大事にしているんですけど、見た人の人生に何かきっかけを与えるようなステージになってほしいと願っています。
◆同時期に放送される他局の大型音楽特番を意識されていますか?
宇野:もちろんです。同じアーティストが同じ楽曲を披露されることもありますし、ファンの方はよく見ていますから、見せ方が大事になってきます。ただ、かぶらないものを目指すのではなく、『音楽の日』として何を伝えたいかを大事にして。ファンの方に「TBSはよかった」と言ってもらえるようなものを心がけています。
中川:それこそ『CDTVライブ!ライブ!』をスタートさせるとき、各局の音楽番組と戦っていく中、TBSならではのブランド力をどうやって作って行こうという話をしたんです。そのときに出した結論としては、「アーティストが気持ちよく歌える環境を作ろう」と。そういうわけで、普段の『CDTVライブ!ライブ!』のときから楽曲に対する思いも聞いていますし、それを反映してTBSの音楽番組だと分かるようなトーンを表現できていると考えています。
宇野:もう一つ、『CDTVライブ!ライブ!』をやっている副産物として、各部署の作業がスーパー速いんです。『音楽の日』の準備に入るのはゴールデンウィーク明けからだったりするんですけど、時間がない中でも間に合ってしまうというか(笑)。音楽番組という性質上、今の世の中の動きにアンテナを張りながら、旬なものをお届けしていく意味ではこういうやり方もアリなのかなと思ったりします。
◆『音楽の日』のためにどれぐらいの人数が動いているんですか?
中川:照明スタッフだけで言うと、中継先も全部合わせて80人ぐらいです。各スタジオに15人、中継先は環境にもよるんですけど、30人ぐらいで。技術スタッフ全体で言うと、600人ぐらいの人間が動いてます。
宇野:美術は意外と少なくて、1つのスタジオにプロデューサーとデザイナー、美術ディレクターの3人体制でやってます。それぞれ話し合いながら3つのスタジオでステージを作り、1つの世界観を表現していく。それを統括する立場の私がいてという感じです。ほかの美術スタッフを含めると、やっぱり100人は超えますね。
中川:番組全体となると、トータルで1000人以上が関わっているんです。今回、中継先の能登でお祭りやってる人たちに参加してもらうコンテンツもありますし。やっぱり局を挙げてのフラッグシップコンテンツなので、それぐらい大規模なことになるんです。
◆お2人は当日、どのように迎えるんですか?
中川:僕も照明のオペレーションの1人として参加します。スモークをたいて光線を出したりするから、事前にセッティングしておくのは難しい。臨機応変に動かなきゃいけないところはありますね。
宇野:私は仕事の内容的に本番よりむしろリハーサルまでの方が大変で、「セットのシャンデリアを画角に入れるにはどうしたらいいか?」「アーティストが持参したものを生かして画作りできないか?」みたいな感じで、バタバタしていて。
中川:ある意味、当日にやることがあってはいけないポジションですからね。
宇野:なので私はどこか俯瞰から、視聴者の一人として楽しむ感じで。SNSを眺めていると、視聴者のリアクションが投稿されてくるんです。美術や照明にも注目して、褒めてくださる方がたくさんいて。そういうのもすごく励みになります。
◆今回の『音楽の日』の美術と技術的な見どころをお願いします。
中川:照明的には、光で曲線を描くことはできないかと考えています。「ココロ」にちなんでハートを作るとか、渦を巻く光にするとか。そういう照明を見せたいです。あとはカメラマンですね。楽曲を丸ごと覚えて、ダンサーと一緒に踊るように撮ってるので。表情はもちろん、ここは見せたいという足元もきっちり映しますので、そのシンクロはぜひ見てほしいです。
宇野:美術全体としては、ワクワクやときめきが誕生する瞬間を表現しようと。10メートル以上の長いリボンを使って、直線と曲線の交差していくセットを考えています。リボンというエレガントな素材を使いダイナミックな世界観を作ろうと思っているので、楽しみにしてください。
◆お2人が『音楽の日』に携わっていて、よかったと感じる瞬間はありますか?
宇野:私は始まる瞬間のドキドキ感がたまらなくて。オープニングからセットが映った瞬間、ものすごい感動が押し寄せて来るんです。自分が思い描いたものが形になったからでしょうね。
中川:僕は作業しながらリアルタイムに感動してるんです。何回やっても、音楽っていいなって思える。そういうメッセージ性の強いコンテンツなんだと思います。何より、ステージにいるアーティストが気持ちよさそうにパフォーマンスしているし、昨年SUPER BEAVERさんと合唱した一般の方たちも感動して、泣きながら歌っていたんです。そのぐらい感極まる空間を作れたというのは、いい思い出になりました。
◆お2人自身も音楽が好きなことが伝わってくるんですが、どういうきっかけでこのお仕事に就かれたんですか?
宇野:私は中学3年生のときから、テレビやコンサートの現場で働くことを目指していたんです。もともと絵は得意だったんですけど、美術の先生が美術の道に進むことを勧めてくれて。そのときにはもう、頭の中で音楽番組のセットが動いてました。『うたばん』に関わるのが夢で、毎週VHSに録画してたんです。
中川:VHSですか?(笑)
宇野:ツメを折って、保存してました(笑)。そのために美術のことが学べる高校に行って、その後、大阪で舞台芸術を学んだんです。そうやってこの世界に入ってきたら、最初のお仕事が『うたばん』のセットだったんです。
中川:もう、夢かなってるじゃないですか。
宇野:かないました(笑)。でも毎回、セットができるたびに涙を流してます。自分が思い描いたものが現実になるってすごい感動ですよ。あと、私も割と音楽番組が中心ではあるんですけど、美術デザインってバラエティや『ひるおび』『news23』、オリンピック中継など、いろんなジャンルの仕事を並行してやるんです。そういう意味でも魅力的な仕事だと思いますね。
中川:僕も宇野さんほどではないですけど、結構早い段階からこの仕事をしたいと思ってました。高校2年生ぐらいですね。ライブが好きで、フェスに行ってたんです。同じアーティストが昼と夜で同じ楽曲を演奏していたのに、夜の方がカッコよく見えて。違いは照明しかないと思って、照明をやろうと決めたんです。
◆今まで振り返って、印象的だったお仕事はありますか?
宇野:『音楽の日』で言うと、10回目の放送が一番思い出深いです。宮城県に行って、震災の際に遺体安置所として使われたセキスイハイム・スーパーアリーナから生放送したんです。アーティストの方にもそこで楽曲を披露していただいて。
中川:あれは印象的でした。にぎやかな曲をやっていいのかとも思ったけど、あの場所から送り届けられたことに意義があるというか。
宇野:『音楽の日』の本来の役割を果たせた気がしたし、音楽番組というコンテンツを通して、現地の人たちはもちろん、日本中に思いを届けられたことが一番の喜びでした。
中川:僕もその『音楽の日』が一番ですけど、ちょっと個人的なことも言わせてもらうと、昨年の『輝く!日本レコード大賞』で最優秀歌唱賞を受賞したmiletさんのステージが印象的でした。もともとファンで、誰よりもいい照明にしようと力が入って(笑)。そしたら周りの人がみんな良かったと言ってくれたし、ご本人も喜んでくれたんです。自分が好きなアーティストの世界観が作れるというのは、この仕事の醍醐味だと思います。
◆美術や技術的なことで、個人的にやってみたいことはありますか?
中川:今はもう小型化とワイヤレスが進んで、電源を必要としないし、電波を飛ばすことも当たり前にできるんです。ドローンなんて最たるものですけど、映像だけでなく、スモークや照明設備も付けて演出に使えないかと考えています。
バーチャル空間や拡張現実みたいなものも含め、大事なのは既存のハコにとらわれないことですね。社内に「未来技術」という部署があって、そういうものを一緒に開発してるんです。V tuberが現実世界に飛び出してくるような映像にできないか、とか。どこかで試しにやらせてもらって、うまくできたらコンテンツに落とし込むと。そうやってみんなで技術を成長させているんです。
宇野:美術的に言うと、一つは街中にあるLEDビジョンです。もうピッチは1ミリ以下になって、間近で見ても粒が見えないぐらい素晴らしい解像度のものが安価で手に入るようになったんです。ラスベガスではLEDを使った球体型のアリーナ施設ができましたけど、こういう技術をどう使っていくか、美術デザイナーとしても問われているところだと感じています。
もう一つはコンセプトアートです。映画やアニメを作るとき、まずイメージ画を描くことでクリエイターたちが世界観を共有するんです。海外ではメジャーな手法でしたけど、日本でもコンセプトアートをなりわいにする人が増えて、それこそTBSのドラマでも描かれるようになってきているので。バラエティや音楽番組でも使ってみるのもいいのかなと考えています。
◆お話しを聞くと、日々どんどんできることが広がっているんですね。
中川:そうですね。ライブとテレビの垣根もなくなって来ましたし、ずっと同じやり方では淘汰されてしまう、ものづくりのプロが残っていく時代になったと思います。何をするにも技術の専門知識を持った人間が必要になってきたし、興味があるからやってみたいという若手も増えているんです。技術の勉強のためほかの会社に出向させるみたいなこともしていますし。物事を多角的に見られる人には向いているし、目指してほしい仕事だと思います。
PROFILE
中川清志
●なかがわ・きよし…1984年生まれ。新潟県上越市出身。技術プロデューサー兼照明デザイナー。担当番組に『CDTVライブ!ライブ!』『テレビ×ミセス』『輝く!日本レコード大賞』など。
宇野宏美
●うの・ひろみ…1982年生まれ。香川県丸亀市出身。美術プロデューサー兼美術デザイナー。担当番組に『輝く!日本レコード大賞』『音楽の日』『news23』など。
番組情報
『音楽の日2025』
TBS系
2025年7月19日(土)後2・00~9・56
©TBS